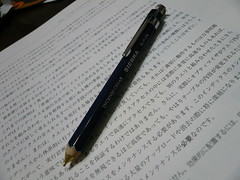JPEdをUbuntuにインストールするときの備忘録。デスクトップ環境はGNOME。ちょっとはまったのでここに残しとく。
インストール
JPEdの最新版をダウンロードする(Main branch)。
ダウンロード先はココ。
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=171576
インストール
$ mkdir ~/tmp
$ mv ~/デスクトップ/JPEd-1.0.1_install.jar ~/tmp
$ cd ~/tmp
$ chmod +x JPEd-1.0.1_install.jar
$ java -jar JPEd-1.0.1_install.jar
...
... あとはインストーラの指示に従う
... インストール場所は ~/app/JPEd-all にした
ここまででJPEdのインストールは終了。はじめは~/デスクトップにダウンロードして、そこでjava -jar JPEd-1.0.1install.jar_したけどインストーラの起動中に落ちた。原因はディレクトリ名に日本語を含んでいたから。jarの展開中にインストールに使用するファイルが見つからなくて落ちていたよう。ちょっとしたハマりポイント。
起動
普通に起動
$ cd ~/app/JPEd/bin
$ chmod +x JPEd.sh
$ ./JPEd.sh
...
... あぼーん、起動中にヌルポで落ちる
...
$ java -version
java version "1.6.0_03"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_03-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.6.0_03-b05, mixed mode)
java6だと何かのバグで落ちる。どっかで見たことがある。でjava5にして再トライ。
$ sudo update-alternatives --config java
`java' を提供する 6 個の alternatives があります。
選択肢 alternative
-----------------------------------------------
1 /usr/bin/gij-4.2
+ 2 /usr/lib/j2sdk1.5-sun/bin/java
3 /usr/lib/j2sdk1.4-sun/bin/java
4 /usr/lib/j2sdk1.6-sun/bin/java
5 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java
* 6 /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
デフォルト[*] のままにするには Enter、さもなければ選択肢の番号のキーを押してください:
jvmのバージョンは沢山インストールしてるw。5を選択する。そして起動。
$ ./JPEd.sh起動できた。でも見た目がいまいち。Swingのデフォルトルックアンドフィールはヒドイ。java6から綺麗になっているという話を聞いたことがあるのでjava6で起動したい。
色々調べるとlocaleの設定があ ja_JP だと駄目らしい。ということでjava6に戻して下を試す。
$ LANG=Cen_US.UTF-8
$ ./JPEd.sh無事起動。JPEd.shにLANG=Cen_US.UTF-8の記述を書いてオシマイ。
変更: 日本語を入力できなかったので、記事の終わり部分を修正。